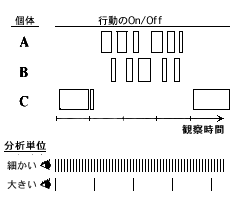
図1 観察される行動パターンと分析単位の関係
時報のチャイムが鳴っている。同じ音程で鳴り響いている。ぼくは気にも止めずに書き続ける。とつぜん、抑揚が頭の中にわきあがる。小さい頃から数え上げるときに使っている、あの旋律じみた抑揚だ。しいち、はあち、ぼくは子供がやるように数え上げる。くう、じゅう、じゅういち。時計を見る。11時。どんぴしゃりだ。
少なくとも、6まではまるで数えたおぼえがない。かといって、そのときぼくは1、2、3、4、5、6と、自分がそこまで行った数え上げを大急ぎで復習したのではない。そこまでの行為は切り分けることのできない塊として、あたかも途中まで歌われた歌のように、ふいに頭の中でたちあがり、そのときはもう、次は「しいち」だとわかった。そしてぼくは自分がチャイムを聴き始めたときから、じつはうわの空で数えていたことを知る。
この、抑揚とともに現れる不可分な塊のような数、不可分な塊のような行為のことをベルクソンは「質的多数性」と呼ぶ。そして、1、2、・・・と切り分けることのできる「数的多数性」と区別した(1)。彼のいう「持続」とは、この二つの「多数性」が同時に明らかになり、引きはがしがたく互いに浸みだしている状況、たとえば上のような事態を指す。
行為が、分かちがたい塊としてわが身にせまってくる。その衝撃が、ベルクソンをして「持続」を考えさせ、「持続」のありようにこそ生の秘密があることを確信させた。
「質的多数性」それは抑揚、つまり声としてふいにやってきて、数をわたしに想起させる。誰の声か。その声はわたしの身体にたちあがり、わたしにそれまでの行為をまるごと受け取らせる。わたしはこの身体抜きに、この行為が不可分だと気づくことはできない。
声の一撃。メディアがメディアとして異物のようにたちあがり、行為をもたらす。数は身体とともに現れ、行為が明らかになる。
わたしたちは、そのように数えているだろうか。
たとえば、音を聴く。サウンド・スケープという考え方を打ち出したマリー・シェーファーは、良き音の観察者でもある。彼のように、音を聴いてみよう。
「たとえば、車の警笛。ある一定の時間、たとえば十分間、その数を数えてみよう。ものを数えるのが好きな子どもには特にいい練習になるが、誰にとっても役に立つ。この課題をやってみると、警笛が実にさまざまなつかわれ方をしていること、時には会話のようにつかわれていることにも気づくだろう。」(2)
平易な文章だが、じっさいに試してみるとおもしろいことに気づく。
警笛ははじめのうちは、1回、2回と、自動的に数詞を与えられていくだけに過ぎない。しかし、そのひとつひとつの響きの差に注意が向くに連れ、感覚は変わっていく。ひとつ鳴るたびに、さきほどより高い、低い、大きい、ふくらみがある、などと感想がわきおこってくる。その取り合わせが、しだいに妙なおかしみをたたえているような気がしてくる。
そして、数え忘れるのだ。いや、正確には、一瞬、数詞が頭に浮かばなくなる。ぼくはあわてて「数える」という課題を思い出す。いまいくつだっけ。忘れたメロディを取り戻すように、またしても、あの数え上げの抑揚がやってくる・・・はちじゅろーく、はちじゅしーち、はちじゅはーち、危ういところでなんとか数え上げていく。
マリー・シェーファーは、注意して読むと、このような感覚の変化を導くために周到な設定をしている。最初は数えさせる。そして「さまざまなつかわれ方」、つまりは警笛どうしの差を喚起させる。10分という時間は、通常の人がじっとしているにはかなり長い時間だ。長すぎる時間だからこそ、感覚の変容がやってくる。警笛と警笛が、ひとつふたつと数えることのできない、一連の「会話」として聞こえてしまう瞬間がやってくる。警笛どうしは、じっさいには「会話」していたのでなく、でたらめに鳴っていたに過ぎないかもしれない。しかし、いくつかの警笛たちが、あるタイミングでお互いの差を浮きだたせるよう時間的に配置されたとき、それが、不可分な現象としてこちらの耳に届く。
観察者は、観察するということになにがしかの信頼をおいている。行動学者にせよ、文化人類学者にせよ、エスノメソドロジストにせよ、おそらくこのことに変わりはない。観察し続けることで、そこに不可分な現象が現れるのを待っている。不可分な現象は命名される。その不可分なできごとが観察者の身体を通ってきた証しに、「投げる」「取る」「そっぽを向く」「離れる」などと、行為を表す述語があてられる。
その不可分な行為は、観察される側にとっては単なる偶然に起こったできごとの寄せ集めかもしれない。観察者が手前勝手に感じ取ったできごとに過ぎないかもしれない。
観察者は、観察し過ぎるほどくり返し観察することで、偶然のできごとにつかまるのを避けようとする。何度も違う場にでかけ、あるいは何度も同じ場の映像や音声を再生し、なにもそこまで細かく分けなくてよいだろうというくらい、目の前のできごとを数え上げる。こうした行為を通じて、まず、これまで不可分だったと思われていたできごとがいったんばらばらになる。そして、観察をくりかえすうちに、ばらばらの断片から、ある不可分なまとまりが身体にたちのぼってくる。観察者はそのようにしてたちあがってくる不可分な衝撃にだけ、名前を与えようとする。
行動学の主たる営みは、観察や実験によって、できごとを数え上げ、名づけ、不可分な行動として扱って行くことだ。では、現代の観察法は、こうした営みに対してどのように配慮されているだろうか。そこでは時間はどのように扱われているだろうか? そのことで、観察はどう変わるだろうか? 以下、動物行動学の場合を中心に、観察から分析までの手続きを検討していこう。
動物行動学では入念に予備観察をして、その動物のふるまいをカテゴライズし、名づける。このようにしてできる行動目録のことを「エソグラム」と呼ぶ。この考え方は現在では、人間の行動を扱う心理学などの周辺領域にも広まっている。
教科書をひもとくと、エソグラム=「その動物種特有の、ある決まった行動パターンを抽出していくこと」という図式にしばしば出会う。
「ちょっと見ただけでは、いろいろな鳥や魚はどれも同じような行動をしているように見えるかもしれない。あるいは、行動というものは複雑過ぎて、とても簡単にタイプ分けなどできないと思うかもしれない。だが幸運なことに、ほとんどの動物ではこういった印象は完全には正しくない。どの種も一連の定型的な行動パターンを持っていて、そのいくつかは近縁種と共通だが、他のものはその種にしか見られない。行動のパターンを記載して、それが現われるたびに認識することは、案外難しくないことなのだ。」(3)
動物の行動パターンは動物の側で分節化されていて、それは周到な観察や実験によって、その通りに取り出されるにちがいない。そのような信頼感が、ローレンツやティンバーゲンら古典的なエソロジストの著作からは感じられる。
しかし、じっさいに行動をカテゴライズするのはなかなかむずかしい。
まず行動パターンをどれくらい細かく分けていくかという問題がある。
たとえば、ニホンザルにおいて、ある場所からある場所へ移る行動をすべて「移動」と記載してしまうことはできる。しかし、注意深く観察していれば、目の前のできごとは、「移動」といったおおざっぱな形で不可分性を感じさせることは、あまりないだろう(もちろん、カテゴライズが終わった後、便宜上、いくつかの行動を「移動」として扱うことはできるが)。逆に、ある雄どうしが接近して離れるまで細分化して、腕の上げ下げ、顔の微妙な向きにいたるまでを細かく命名していくことだってできる。しかし、こうした精密すぎる命名もまた、不可分だったはずのできごとを観察者から遠ざけていくかもしれない。複雑な四肢の動き、表情の動きの組み合わせを「あいさつする」「威嚇する」とひとまとまり分類する方が、観察者が感じた不可分性に近いこともある。
どれくらい細かく行動を分類していくとできごとを捉えやすくなるかは、どのような仮説を立てるかによって変わってくる。しかし、まず仮説を立て、それを観察によって検証していくという教科書的な進み方だけが起こるわけではない。仮説はある観察によって修正を加えられ、新たな仮説によって次の観察のあり様が変化していくことになる。ある思い込みで観察をしていると、前の観察では感じられなかった不可分性が、できごとどうしに感じられることもある。それが、次の観察では、そうした感覚が立ち消えてしまうこともある。仮説と観察の往復を繰り返すうちに、やがて、何が不可分な行為として感じられるかが、絞られてくる。そこでようやくエソグラムらしきものが書かれるというのが、行動観察の実情ではないだろうか。
そして、観察者によってこうした観察の営みのありようは変ってくるに違いない。じっさい、最近の教科書には(4)エソグラムに載っている行動カテゴリーの数や詳しさは研究者によってかなりばらつきがあることが指摘されている。
また、何をその個体群に共通の行動とみなし、何を個体間変異とみなすか、という問題もある。
観察の際、いままで見たことのないできごとが目の前で繰り広げられることがある。こうしたできごとはどう分類したらよいか。必ずしも個体変異とみなせるわけではない。むしろ、特定の文脈で必ずその個体群に現われる行為なのかもしれない(観察者はしばしば、後者のように考えたい誘惑にかられる)。
もし個体間変異だとすれば、それは従来考えられてきた行動パターンとどう関係し、そこからどうずれているのか。個体群に共通の行動だとすれば、どのような「特定の文脈」によってそれは現われるのか。
研究を事後的にふりかえれば、これらの判断はある程度の整合性をもって行なわれているようにみえる。しかし、じっさいには、こうした分類は、観察や分析の過程で次第に観察者の頭の中でその都度再構成されていくものだ。
それまでのエソグラムにいくつか記述の欠けがあってそれが新たな行動によって埋まるのなら楽だが、そうとも限らない。箱に風船を詰めていくと、詰めるごとに各風船の配置が変わるように、ひとつの新たな行動が見つかると、その効果は多かれ少なかれ、それまで考えてきた行動パターンどうしの関係全体に波及する。
エソグラムを作ることは、観察対象である動物のふるまいを、人間の認知能力を駆使して分節化していくことでもある。だからエソグラムについて考えることは、観察する側である研究者自身が、どのような分節化をほどこしやすいか、そしてどのように分節化することで何が把握しやすくなるかを考えることでもある。
エソグラムを詳細にとればそれでよいわけでもない。エソグラム自体の有効性は限られたものだ(4)。それでも、くり返しエソグラムのあり方を検討することは、観察者が不可分なできごとに出会うために必要なことだ。
いったん、不可分なできごとに名前がついてしまうと、それはひとつの行動として扱いやすくなる。その行動が起こる兆し、終わりの予感が観察者の中にたちあがるようになる。こうなると、行動学者はチェックリストを作って、特定の時間にその行動が起こったら、すばやく行動の開始、終了をチェックすることができる。
じっさいには、それらは、コンマ一秒単位のすばやいできごとだったりもする。つぎつぎと起こるすばやいできごとを前にすると、研究者は、ともすれば自分の見出したいものに注意が行ってしまいがちになる。これを避けるために、最近の観察法には、問題となる行動をなるべく時間内で均等に観察するよう、さまざまな約束ごとが設けられている。
観察時間という時間の流れはまず、細かい等間隔の単位時間に分けられる。観察者は単位時間ごとにその行動が起こっているかどうかをチェックしていく。単位時間の取り方は、フィールドの状況や観察方法によって変ってくる。双眼鏡で広々とした草原をスキャンしながら動物の居場所を確認していく場合、単位時間はせいぜい分単位になるだろう。一方、キーボードを使って目の前の行動を次々と入力していく場合は秒単位になるかもしれない(観察者が行動を見てからキーを押すまでの時間にコンマ1、2秒の誤差があるからだ)。とにかく、一度、単位時間の長さを決めたら、各単位時間ごとに目の前のできごとをチェックする。こうすれば、まんべんなく行動を観察できる。
ここで注意したいのは、行動を記録する際にとるサンプル単位時間と、分析の際にとる分析単位時間は、別のものだということだ。そして、分析単位時間は、短いほどよいというわけではない。
たとえば、3つの個体A,B,Cの行動について、図1のような時間分布を考えてみよう。この分布から、3個体の行動はお互いにどのように影響していると言えるだろう?
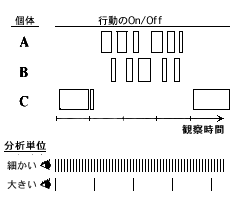
ひとつの簡単な答え方は、「AもBもCも、お互いに行動が重ならないようにしている」というものだ。これはこれで正しい。しかし、こうも言えないか?「AとBはお互い同調しているが、CはAとBに対して行動が重ならないようにしている」
前者の考え方は、単純に分析単位を細かくして、ひとつひとつの単位時間内で、A, B, C間に重なりがあるかどうかを考えれば容易に引き出せる結論だ。一方、この二つの考え方は、分析単位時間を変えていくことで得られる。分析単位時間を細かくとった場合が前者で、大きくとった場合が後者だ。
細かく等質な単位時間にばらしてしまうと、観察されたことがなんだったのか、よくわからなくなる。それは、ばらばらになった単位時間どうしの間にどのような関係が見出されるかに関する情報が抜け落ちてしまうからだ。
等間隔に観察時間を区切り、ひとつの解析単位時間を設定することで、行動学は、検証可能な唯一の記述のあり方を手に入れたように見える。しかし、じっさいのところ、どれだけの解析単位時間をとるかによって、得られる知見は変わってくる。解析時間を長くするということは、言ってみれば、一度は等間隔に分割した観察時間の断片どうしを、つなげて考えてみるということであり、長さを変えるということは、断片どうしの間に様々な関係を仮定して行動を分析することにあたる。この結果、ひとつの時系列データから、さまざまな結論が引き出されうるのだ。(5)
ことは行動学だけの問題ではない。時間や空間を適当な単位に分け、その性質を調べるとき、同様の問題が起こる。
たとえば、生物の分布の関係を調べるとき、しばしば調査地を均等にいくつかの区画に区切って、各区画ごとの重なりを調べるという方法がとられる。この方法では、分析する区画の大きさによって、結論が変わってくる。逆にこの特性を利用して、さまざまな区画の大きさをとって分布の性質を考える方法も考案されている。(6)
経済学では、単位時間どうしの関係を考える手法は、株価解析などに見られる。株価は一日のうちにも激しく変動するが、長期的に見ると上昇(下降)しているように見えたり(トレンド)、また季節によって周期的に変化(季節変動)しているように見えることがある。こうしたより長い目で見た株価の動きをトレンドと呼ぶ。そこで、解析単位時間を長くとって、これらの傾向を抽出しようとする。
つまり、均等に分けた単位時間をいかに結びつけるかについては、さまざまなやり方があって一通りではないのだ(7)。
行動をいかにカテゴライズするかは観察者にゆだねられている。また、観察時間を分割し、それらを関係づける方法も、いかにシステマティックになったとはいえ、本質的にはこれまた観察者にゆだねられている。
画像や音声の記録装置の向上は、より誤差の少ない精密な観察を研究者にもたらす。しかし同時に、設定しうる分析単位時間の数は増し、単位時間どうしの組み合わせの数は増え、そのバラエティはますます増大することだろう。つまり、記録装置が進歩するに従って、観察者は単位時間に対して、より多くの組み合わせについて考えをめぐらさねければならなくなる。つまり、記録装置の向上は、ありうべき結論の数を減らすのではなく、むしろ増やしていく。命名された行動をただシンプルにとらえるというよりは、ひとつの行動がより複雑な様相を含んでいくことが予想される。すなわち、テクノロジーの進歩が動物の行動をよりクリアにしていく、という直線的な科学史観とは裏腹に、記録機器の進歩によって、観察という行為は、ますます迷路へとさまようことになりかねないのだ。
もちろん、それはさまざまな不可分なできごとへの出会いの可能性が広がったということでもある。しかし、それが、単に手続上浮かび上がって来るできごとに過ぎないのか、それとも、観察者がフィールドで、またはある種の再生装置を通して、自分の声、自分の身体をなぞるように感じるできごとなのかは、常に自省される必要があるだろう。
いまや(というより今も昔も)研究者にとって本質的な問題は、研究者の身体にどのような不可分なできごとが立ち上がってくるか、ということだ。ローレンツが楽しげに、あるいはしつこいほどに克明に語る、動物のふるまい。彼のことばがいまも有効であるとすれば、それは彼のことばを読むことで、読者であるわたしたちの身体が、そこで命名されていく動物たちのふるまいを読みながらむずむずと動こうとするからだろう。
フィールドにいるうちに自分の身体に必ずや不可分なできごとがたちあがるにちがいない。そのことで自分の身体をとらえなおそうとする。そういう身体観を抜きにして観察という行為を語ることは難しいだろう。
もともと、研究者は、自らが気づかなかった身体を発見したかったのであり、観察者の恣意性が観察や分析の段階で入ってくることは、むしろ研究においては避けがたい事態だ。文化人類学者が異文化にでかけることも、エスノメソドロジストが日常生活でかわされる会話を詳細に記述することも、できごとの一撃に立ち会い、それが自分の身体を通って、不可分な行為として感じ取られる、そのことで自分の身体を復権しようという行いではないだろうか。
まして、人間以外の動物を扱う行動学の場合、発生上、あるいは機能上、人間とまったく異なるかもしれないその動物たちの身体をあつかうことになる。そのありさまを、観察者は自分の身体にたちあがってくる不可分のできごととして翻訳していくのだ。動物たちの身体が観察者にもたらすさまざまな手掛かりをあえてアフォーダンスと呼ぶなら、それらのアフォーダンスは、もしかしたらノーマンがドアのノブの持つアフォーダンスに導かれて引くべきドアを押してしまったように(8)、わたしたちをとんでもない解釈に連れていくかもしれない。
それでも、観察者は、観察対象である動物に、人間となんらかの共通項があることを期待する。動物たちの身体は、人間の身体と同じではないからこそ、わたしたちの身体に、「質的多数性」と「数的多数性」を同時に呼び起こし、思いもしなかった不可分性に立ち会わせてくれるにちがいない。動物行動学者はそのような信頼を、動物たちに寄せる。
そのように、人間が人間以外の動物のふるまいに信頼を寄せる。「進化」ということばは、そんな場所で輝くのではないか。
【注・引用文献】
(1) ベルグソン 「時間と自由」平井啓之訳 白水社
(2)R.マリー・シェーファー 「サウンドエデュケーション」 鳥越けい子・若尾裕・今田匡彦訳 春秋社(1992)。
(3)P. J. B. スレーター 1985/1988 「動物行動学入門」 日高敏隆・百瀬浩訳 岩波書店
(4)P. マーティン・P.ベイトソン 1985/1990 「行動研究入門」粕谷英一・近雅博・細馬宏通訳 東海大学出版会
(5)Hiromichi Hosoma 1989 A new analysis method for the comparison of 2 temporal patterns, with indices of association.
(6)こうした「区画法」に関する数学的な議論については、長谷川政美・種村正美 1986 「なわばりの生態学」 東海大学出版会 を参照のこと。
(7)ここではもっぱら「区画法」に話を限ったが、データ間の空間的距離を考える「距離法」あるいは、単位時間どうしの関係を時系列の方向を考慮に入れて考える「連鎖」分析などもある。推移行列を使った解析やマルコフ連鎖モデルを使った解析などが後者の例として挙げられるだろう。
(8)D.A.ノーマン 1988/1990「誰のためのデザイン?」野島久雄訳 新曜社
(9)K.ローレンツ 「動物行動学」全四巻 日高敏隆・丘直通訳 思索社